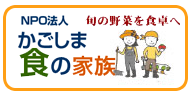2012年11月29日
世代間ギャップ
冬の野菜にがらっと変わりました。
あれほどまでに活躍した杉村さんのオクラやピーマンは収穫がほぼ終わりました。
野菜が少ない時期をよくがんばってくれました。


野菜の種を蒔けば数日後に芽が出てきますが、同じように草の芽も顔を出します。
両者は競うように大きくなり、野菜の生育が遅いようだとあっという間に雑草も追い抜かれてしまいます。
そこで何か手を打たないといけないんですが、すぎむら農園では種を蒔く列の間隔をひろく取って、そこを除草機械が走れるようにしています。
雑草の芽がでてすぐぐらいは機械でぱーっと通れば土を耕して草をやっつけることができます。
しかしそれが遅れて草が大きくなるとうまくいかないことがあるので、息子のみちおさんは早め早めに機械をひたすら走らせているそうです。
それを見たお父さんは「みちおは畑の中を走っている。農業はそんなに急いでやるもんじゃない」 「百姓が草を取らんでなにを取るのか」と、ノムラ監督みたいにぼやいているのです。

つまりお父さんに言わせれば、草が大きくなってからそれを取ることこそ百姓の仕事だということのようです。
さすが合理化を考える若者には理解不能な深いコメントであります。
世代間ギャップを埋めるのにはみんな苦労しています。
でもそれぞれでよいと思います。
そんなとき息子は・・・ 日曜日の生命の祭りでオリジナルCDをリリースする中村てつろうさんと歌を熱唱していました。



2012年11月28日
変わらない祭り
今朝は霜が降りたようで、勢い旺盛だったハヤトウリの葉が黒っぽくなりました。
日曜日は今年で27回目の「いのちの祭り」が中央駅近くのライオンズ広場であります。
オーガニックフェスタのような大規模イベントではありませんが、有機生産者が昔から参加を続けている収穫祭です。
いのちの祭りといえば私たち兄弟にとっても小さい頃から参加している一大イベントでした。野菜や米、加工品などをみんなこぞって販売します。
何回かは兄弟が力を合わせて作った「フライドいもポテト」というものを売ったことがありました。さつま芋を細く切って油で揚げたおやつです。
これが本当に美味しかったのか、同情で買ってくれていたのかは定かではありませんが、けっこう売れていました。こどもたちにとっては小遣い稼ぎのよい方法でしたね。
小遣い稼ぎの資源があるっていうのは楽しいことです。
中学の頃にはニワトリブームというのがあって、友達が家の庭で鶏を飼い始めたのをきっかけに数人が鶏飼いにはまり、卵をとったりして楽しんでいました。
うちでもウコッケイという鶏をもらってきて育てて、高校に自転車で通う途中、有機野菜のお店「地球畑」に卵を届けては売ってもらっていました。
あれから15年。
有機百姓のこどもたちは大人になって親の跡を継ぎ、それぞれのやり方で世代交代をしようとしています。
でもいつまでも変わらないのがこの祭りですね。
自分のこどもにも語り継いでいこうと思います。
2012年11月26日
農的キャッシュフロー

タマネギは時間がかかるよね~
と昨日も話していたんですが、それもそのはず。
種まきをするのが9月で、それから水をかけたり雑草を取りながら育て、えんぴつぐらいの苗の太さになってから植えるのがちょうど今頃です。

冬のあいだはほとんど大きくならず、暖かくなったら葉が茂り始め、春になって最後のラストスパートでようやく玉が太り始めます。
その期間は実に半年!
時間をかけて育てるからこそ大事に、丁寧に育てなければならないです。
だからというわけではないのですが、去年まで機械を使って苗を植えていたものを今年は全部手作業植え。その数2万本! 研修生がよく頑張りました。
機械はトラブルも起こりますが人の手ならその心配はいりません。
研修生もその作業を体験しながら自分たちでも畑を借りて作り始めています。
でもまず種を買って育てて、野菜を収穫して販売して、費用を回収できるのが半年後というのは新規就農者にはきついですね。

農業は食いっぱぐれないとはよく言いますが、出ていくお金と入ってくるお金の動きがよく分かっていないと、種代や肥料代が先にどかんと請求されて払えないということも考えられます。
野菜の作り方ももちろん教えてあげないといけませんが、そういうお金の流れ(格好よく言えばキャッシュフロー)や他にも教えることは山ほどあります。
農業をしたい人たちが昨年以降ますます増えてきているようです。
その人たちの受け皿として、現役農家たちはどう受け入れていくのかもこれから問われてくると思います。
2012年11月21日
採算とれるのか
あちらこちらで皇帝ダリアが満開で見ごろを迎えています。
イチョウも色づいてきましたね。

皇帝ダリアは多年草といって、霜が降りると枯れてしまいますが、また来年には同じ株から芽が出てきます。

畑ではキャベツの収穫が始まりました。今年は品種を変えたせいか生育が例年より遅れていて、かつ収穫時期にばらつきがあるようです。
キャベツは秋に無農薬で作ろうと思ったら虫をシャットアウトしないとできません。防虫ネットを被せて育てています。

湧水町の畑にはたくさんのキャベツが並んでいますが、収穫時期が揃えば楽をします。畑の手前から順番に収穫していけばいいだけです。巻く時期がばらつくと畑全体から選んでとらないといけないので手間がかかります。
ましてネットをはがしたりまた被せたりも二度手間なので、できれば揃ってくれたらありがたい・・・
と考えるのは人間のエゴなので、野菜たちが育ちやすい環境を提供して、あとは自然のままに収穫を迎えるのを待つだけです。
きのう地元のスーパーに行ったら丸々したキャベツが1個100円でセールをしていました。
おそらく農家の手取りは50円あるかないかでしょう。
それで採算が合うという人もいるんでしょうが、うちは違います。
夏の種まきから自分で苗を育て、その間も害虫対策と雑草対策をずっと取りながらやっと収穫を迎えたので、もちろん100円とかでは売りたくないし、ちゃんと理解していただける方に買ってもらいたいと考えています。
これから先、大型無農薬農業ができあがって1個100円でもいいよっていうぐらいになれば消費者としても嬉しいと思うので、なるべく良い物を安くで提供できるように努めたいと思います。
でもダイコン1本100円ならともかく、1個100円で採算の合うキャベツってどうやって作られているんでしょうね。
今週後半からまたぐっと寒くなりそうです。
風邪には気をつけて元気に過ごしましょう!
2012年11月19日
にら終了
先週からやや寒い気候に入ってきました。
霧島連山の紅葉が徐々に見ごろを迎えています。
その霧島連山の西の端に位置するのが栗野岳ですが、もはや冬の張り詰めた空気に変わりました。
少し遅れたキャベツの収穫が始まりました。

冬野菜の収穫をしながら人参の草取りや間引き作業が続いていきます。
寒い中での人参の間引きと草取りは栗野岳農場の年中行事というもので、たんたんとした単調作業で無心になります。ピーンと張った空気で耳を澄ませば・・・
静かさや 畑に響く 鹿の声
パクリ川柳でした。今日もにんじんをシカにやられました。
ついに最後まで残っていた夏の野菜が終了となりました。
きのう食の家族の事務所に一枚のファックスが届きました。
「ニラは今日で完全終了しました」と一文。
父の国光氏からでした。
別所帯になればこんなこともファックスでくるのかよと思いながらニラの畑を見に行くと、確かに一部のニラが寒さ特有の症状で黄色くなっていました。
そして夏どんなに暑くてもぐんぐんと伸びていた葉は勢いがなくなっていました。冬到来のサインでした。
ニラは冬の鍋物にもよく使われる存在ですが、旬は夏場です。
冬はハウスで暖かくして育てないと作れません。

食の家族での位置づけは夏場で葉野菜がとれない時の定番というか、夏のあいだ中、お声がかかればいつでもセット野菜に登場してくるといった都合のいい存在です。
今みたいに小松菜やほうれん草、春菊などが出てくればたちまち出番が減ってしまいます。
そんなニラに対してのねぎらいの気持ちがあってかないのか分かりませんが、あまり上手でない(失礼!)走り書きをよこしたのでしょう。
これからは冬が旬の葉っぱものを楽しみましょう!
2012年11月14日
オーガニックフェスタ

明日ぐらいから寒くなるようで、冬らしくなりそうです。
日曜日のオーガニックフェスタは時折雨が降る中でしたが、最後まで開催することができました。
半年近くにわたって準備をしてきたものが延期なしの1日勝負ですから、雨予報が出ていると実行委員の緊張感もピークです。

しかし雨であろうが関係なくやってくるお客さんもたくさんいたような気がします。とりあえずは無事に終わってよかったです。
今回のオーガニックフェスタは5回目でしたが、定番になったものと、新しい企画がうまくマッチしていたような感じでした。


自慢の農産物を持ち寄っての販売、有機加工食品や自然素材を使った商品も多くの出店があったし、有機食材を使ったランチやパンやスイーツの販売なども定着しました。


シェフの皆さんが工夫して提供してくれたオリジナルメニューはどれも美味しかったです。こだわり素材のスイーツもきれいに並んでいて目をひいていました。


会場では「あそび村」というこどもたちの遊び場があって毎年にぎわっているんですが、今年も新企画のキッズサスケやトラクターアドベンチャーが大人気でした。



定番になった竹の巨大ブランコやアスレチックは数日前に山から切り出した竹を前日の雨の中組み立て、オーガニックフェスタのシンボルとして会場中央に設置されました。
一日で解体するのはもったいないぐらいですが、めいっぱい子どもたちに楽しんでもらえたようです。

若けぇもんの会かごしまもメンバーの活動紹介パネルを展示しました。
左が園山、右が宴会部長のしばちゃんです。
おまけ↓

2012年11月04日
スーパー花じィ
大隅半島の花牟礼さんのところでは「霜が降りたかも」ということ。
今日は久しぶりの雨も降って冬野菜が順調に育っています。
小松菜はぐんぐん伸びて、2~3日後にはかなり大きくなっているんですが、そう思って収穫をあてにしていたら今度はこんな寒さがきて、あまり大きくなっていなかったりします。なかなか読めないですね~
花牟礼さんにいたっては「春菊はとってみらんとわからんど!」。

花じィはスーパーじいちゃんです。
じいちゃんはこの時期の野菜と一緒で行動が予測不能なので、ひんぱんに連絡しておかないと大変なことになります。
きのうの電話では、
「いんげんのような豆がたくさんあるから持っていくからね!」
と言うから
「その豆はなんですか?」
と聞けば
「食べてみたらけっこう美味しいから、要るんだったら使ってくいやい」
私「いやいや何か分からんからとりあえず今度見本持ってきてよ」
花じぃ「霜が降りたらダメになるからもうズバ採って持っていくから」
私「ズバ(たくさん)わからん豆持ってきても困るよ」
花じぃ「まぁ、とったひこ持っていくからね~」 プー プー
「・・・」
会話がそもそも成り立っていないんですが(笑)
結局なんの豆なのかは分かりませんでした(泣)
でも80歳近い花じぃが携帯を使いこなしてくれているのはありがたいですよね。いつでも連絡がとれますから。
最年長の花牟礼じいちゃんはまだまだ衰える気配はありません。
2012年11月02日
コメ事情

フェスタを皮きりに4週続けての“祭り”、そして年末まで結婚式にも4回出席予定で、あっという間に正月がきそうです。
元気の源は食卓に山盛りの自家製野菜と新米でしょうか

年末まで突っ走ります

新米は自家用ぐらいしか作っていませんから、今の広さでは家族全員をまかないきれなくて、最後のほうはコメ農家の澤田さんから買ったりしていました。
澤田さんや橋口さんみたいに田んぼに合鴨とかジャンボタニシを入れていないので、雑草は田車だったり手で取ったりの繰り返しで、特にヒエは種を落とすと来年が悲惨なことになるので必死に毎年取ります。
この草取りが夏の一番暑いときの“イベント”なんです

もっと楽な方法はあるんでしょうが、あえてこの面倒な作業をするというのは、米作りの大変さを忘れないためです。
米作りはどんどん便利になって、大農家は田んぼに足を踏み入れることなく収穫までできるようになりました。


トラクターで代かき、乗用田植え機で苗を植え、農薬撒くのも米どころではヘリコプター散布が当たり前。収穫もコンバインで一気に刈り取って機械乾燥。
自家用だからのんびり手で草取りをしていられるんでしょうが、米で飯を食うには(少々変な表現
 )そんなことをしている暇はありません。
)そんなことをしている暇はありません。こんな大農家であったってそうそう儲かっているわけではない、というのが日本のコメ事情ですよね。設備にはお金がかかっています。
高級外車が簡単に買えてしまうような大型機械の値段と、低迷する米価とのギャップ・・・
私は自分で作って自分で食べるぐらいがちょうどいいです。
手をかけて世話した新米の味は格別です