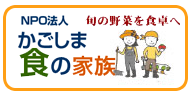2015年02月18日
収穫まで4ヶ月
トマト、なす、ミニトマトの種を蒔きました。
ミニトマトはうちの事務所の“ソムリエかわさき”からの要望があったのと、森のかぞくの作太郎シェフからぜひ作ってくれということだったので、細長くて甘い「アイコ」を蒔いてみました。

有機野菜を取りいれてくださる飲食店も増えてきたので、彩りを考えたカラーピーマンなどにもチャレンジする予定です。お楽しみに~
白菜、キャベツと終わりが見えてきました。
暖かくなると花が咲いてしまうんです。
白菜なんかは割って中心のところを見てみれば、もう芯が上がり始めています。
何年か前の話ですが、それはたくさん野菜を使ってくれるお店があって、大根どっさり、白菜どっさりって感じで配達していたんです。
でも白菜どっさりはさすがに使いきれなかったんでしょうね。
1週間前に届けた白菜が倉庫に置かれたままになっていて、なんとその白菜の中からどでかいつぼみが外葉を突き破って顔を出していました。
お店の人は「これはいい!」と言って飾っていましたよ。
数日後には花が咲き誇っていました。

植物の生命力はすごいです。
土に根を張っていなくてもタネを落とそうとするのですからね。
さて、これから夏野菜の種まきが続いていきます。
といっても畑に種を蒔いているわけではありません。
暖かいハウスの中で種を蒔いてまずは育苗します。
これから2ヶ月ぐらいのあいだ、毎日温度と水の管理をして、いい苗を植えられればそこから2ヶ月がんばっての収穫です。
2015年02月14日
求む、ごぼう名人
来週明けは少し気温が上がりそうですが、天気はくずれそうです。
暖かい雨が降るとこれまでじっと動かなかった野菜がぐ~ん!とのびます。
やっと春らしくなってくるんでしょうか。

久木田さんのさつま芋→紅はるかは、そろそろ終わりが見えてきました。
年明けには種芋をハウスにふせこんで芽を出して、今年植える用の苗を育てます。

1個のさつま芋を土にうめこんでおけばそこから数十本の苗が採れるので効率はいいです。

が、久木田さんがさつま芋を植える畑は半端じゃなく広いので、苗を育てるハウスだけでもかなりの広さがあります。
暖かくなれば芽が動き出して4月から苗植えがスタート、ゴールデンウィークあたりがさつま芋農家はピークの忙しさです。
さつま芋は安定してるな~と思ったのは、去年夏の長雨と台風によってほとんどの作物で平年よりも収穫がわるいという結果が出ていたのに、さつま芋はほとんど影響を感じさせなかったことですね!
台風銀座の鹿児島で盛んにつくられているのは芋作りに適したシラス台地であるのと同時に、悪天候に動じないという強さがあるのでしょうね。
去年を振り返れば夏野菜の実がなるものは長雨に泣き台風にも泣き、お米も日照不足でコケる。安全パイであったはずの里芋も見た目は葉が大きく茂ってよかったかと思いきや掘ってみると収穫が少なかったです。
鹿児島では夏野菜が台風リスクなどで安定しないということがあるので、春に植えて秋収穫する土ものは貴重な収入源です。それをこれから植えていきますよ。
ただし、今年はごぼうを作れる!という人がいませんでした。
ごぼうの長さまで深く耕せる機械と、収穫のときに掘り上げる機械がないと作れないんですよね~
庭がある方は短いごぼうの種を買ってきて蒔いてみてください。
手で引っこ抜けるサイズなら自分でも作れます(^^)
2015年02月11日
作付会議 IN 出水
先週末からの寒波は今年一番でしたね。
野菜も午前中は凍っていて収穫もできません。
来週頃からは暖かくなりますかね~
先週の作付会議&杉村農園見学は天気こそもちましたが、雪がちらつく中で今年一番の冷え込み。標高の高い畑では海からの風が冷たいでした。

一番の驚きは小松菜などの葉野菜がこの時期に青々と育っていることでした。
真冬には種まきができないので、冬採れ野菜は全部秋のうちに種をまいてしまいます。

通常年内に収穫が終わってしまって、2月ぐらいには葉ものがなくなってしまうんですが、杉村さんの畑では過密に種を蒔くことで生育ス
ピードを落とし、今頃まで持たせているという、ある意味では高い技術を駆使していました。

杉村さんの赤土は粘土質で雨が降ったら耕すのもひと苦労、そうでなくても土が塊になっていることが多く、種まきも機械ではあまりうまくいかないそうで手で蒔きます。

草を抑えるビニールマルチも使いにくい畑なので、草対策には人一倍気を遣っていました。
手作業が多いですが、愛車の管理機はめいっぱい動かして草を削り取っているようです。みちおさんの良きパートナーです。

あんな高い山を段々畑に開拓したお父さんは偉いと思いました。
このすばらしい畑は子々孫々受け継いでもらいたいです。

2日間にわたる作付会議では生産者それぞれに色んな考え方があり、同じ有機農業とはいってもやり方はいろいろあるものだと、改めて感じました。