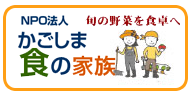2011年12月29日
2011年12月25日
日本酒がうまいお店
 照国神社の近くの赤い屋根のお店です。
照国神社の近くの赤い屋根のお店です。

会員のお店「とまや」さんにも行きました。和食全般なんでもOKという感じの天文館のお店。有機野菜を使っていただいていますが、メインは魚を使った和食。そして日本酒がなんと言っても美味しい



魚料理と日本酒なら「とまや」です
 天文館アーケード(南国タクシー)のあるところから電車通り方向に向かって一本目の細い筋を入っていくとあります。
天文館アーケード(南国タクシー)のあるところから電車通り方向に向かって一本目の細い筋を入っていくとあります。 2011年12月21日
農的暮らし
農業という仕事は日の出とともに始まり、日暮れまでの仕事と思われているところがありますが、実際は日中にしかできない仕事を明るいうちにして、暗くなってから小屋の中での袋詰めなどをすることもあります
そんなことを言いながら、作業効率がわるくて遅くまでかかっているというパターンもありますが・・・ (^^;)
いずれにしてもあさってからは昼間の時間が長くなってくる!
そう思うだけですでに夏を意識してきます。
野菜も寒さとともに美味しくなっているようです。
畑でにんじんを抜いては生のままかじってみるんですが、やっぱりにんじんの旬はまさに今からですね。甘いです!
そしてさつま芋も味が変わった!でんぷんから糖へのリレーがスムーズにいって甘さが増してきました。
話は戻りますが、先ほどの農的暮らしをしてる最たる人物がここの生産者にいます。合鴨米の橋口さんです。
米農家ですから夏場から秋にかけては激務・・・ この合鴨をさばいているのが橋口さん
暗いうちから田んぼへ飛び出しますが、日暮れ前にはしっかり家に戻ってだれやめ(晩酌)を開始。夜は9時頃には寝ているそうですから、まだ還暦というわりにはおじいちゃんのような生活をしています
片やうちの若手隊長すぎむらみちお氏は昨日、コープかごしまの店頭販売で夜9時まで野菜を売り続けていたとか。
へろへろになりながら「今までで一番売った~ 」と報告。
」と報告。

2011年12月20日
2000円の赤字
22日は冬至ですね。
冬至といえばかぼちゃ
しかし食の家族の生産者がこぞって作りたがらない?作物のひとつです。
春に種まきするタイプは比較的作りやすいんですが、秋は敬遠されがち・・・
なぜか?夏は植えてからどんどん気温が上がっていくため、葉が生い茂り実が大きくなるが楽しみですが、秋は逆でどんどん気温が下がっていくためいかに前半とばして実を大きくするかがポイントです。
ちょっと植え付けが遅れれば実が大きくなる前に寒くなり、最後には霜が降りて終了!小さいものを収穫すればいいってわけではなく、未熟なので商品としてはダメです
うちの研修生が早くも自分で小さな畑を借りて野菜つくりをスタートさせたんですが、選んだ作物がこの“秋かぼちゃ”でした。
肥料代やタネ代などで1万円ぐらいかかったのに、採れたかぼちゃは8,000円にしかならなかったそうで思いっきり笑ってあげました(*^-^*)
難易度の高い作物をチョイスしてるのでしょうがないと言えばしょうがないのですが、もう少し作りやすいダイコンとか小松菜ぐらいを選んでれば違ったかもしれませんね~
有機農業では「作りたいもの」と「作れるもの」が必ずしも一致しないので、1年生は「作れるもの」から入ったほうが無難かと
走り高跳びで無理して2メートルを跳んで失敗するより、1メーター50センチあたりで点数を稼いだほうが、農業経営的にはいいような気がします
わたしも2メートルを跳んでは散々失敗してきましたから、そういう結論にいたりました。
師走は忙しいですが、日も短いですので十分お気をつけください。
県外の会員さんへも野菜を送っています

2011年12月15日
2011年12月14日
天然の床暖房

日曜日は有機農業の若けぇもんの集まりで山登りをしてきました

菜の花マラソンの練習をかねて大隅半島の白山の急斜面を登り、ふだん使わない筋肉を使ってきつかったです。
頂上でサンドイッチを食べて熱いコーヒーが飲みたいというわれらが会長のわがままを聞いて、やかんとコンロを担いでのぼりお湯を沸かしてカルロスさんの有機コーヒーを飲みました(*^ ^*)
それにしても寒いからとカッパを着て登ったのに、あまりにハードな登山で汗だくになり、着ている物を順番に脱いでいたら最後はすぎむら会長、半そでになっていました。次は1000m級を登りましょうか・・・



冬野菜の収穫もいろいろありますが、早くも来年の夏野菜の準備も始まりました。トマトなどの苗を育てる育苗ハウスを張りました。
気温もさることながら地温も大切で、苗箱を置く土台も天然の“暖房装置”を取り入れます
堆肥を作るのとやり方は似ているんですが、刈り草と鶏ふんなどを混ぜて発酵させ、その熱を利用して苗を育てます。このやり方は国光さん(父)の専売特許で 苗作りを勉強したい人が見に来ます。
苗作りを勉強したい人が見に来ます。
このハウスは冬場に父の聖域となり、一日の数時間はこの中で過ごします。ほとんどの仕事は息子たちに任せてもこの苗作りだけは未だに父のみぞ知る、で謎も多いです
多分、父の最期はこのハウスの中で寝ているような気がします(笑)
と言ってもまだまだ元気なもうすぐ67歳です。
2011年12月10日
堆肥でほかほか
きょうも寒い一日でしたが、体を動かしていたせいかそんなに寒く感じませんでした。
草の山から立ち上る湯気でむしろ暖かいぐらいでした。
仕事は堆肥づくりだったので体がほかほかでした。
清掃業者さんがトラックで次々に刈り取った草や落ち葉をもってきます もう見慣れた光景ですが、それが畑に投入する堆肥の材料です。
もう見慣れた光景ですが、それが畑に投入する堆肥の材料です。
草が積まれてる時点でもう発酵が始まっていて湯気がほかほか
その刈り草に水をかけつつ、土着菌入りの鶏ふんを混ぜて大きな山にして本格的な発酵を開始。途中ひっくり返したりしながら3~4ヶ月じっくり置いて堆肥ができあがります。今日作ったものは来年の夏野菜に使われますよ(^^)
良質な堆肥で美味しい夏野菜ができますように祈りつつ最後に一句。
おおそうじ 捨てず畑へ リサイクル
お粗末でした
2011年12月08日
12/10は皆既月食
冷たい雨になりましたね
雨の中の収穫はたいへんなので、サトイモやニンジンなどは早めにほりあげておきます。
葉野菜もそうですが、雨の中収穫するとその作業はもちろん、それからあとが倍の時間がかかります。洗ったり、泥のついた葉や傷んだ葉を落としたり、それから袋に詰めて・・・ というところです 露地野菜の宿命ですかね
露地野菜の宿命ですかね
いや~太陽の日があたるっていうのはありがたい

この秋は雨が多かったからそれが身に染みましたよ(;▽;)/
今度の土曜日(12/10)は皆既月食 があるんだと、うちの農場スタッフたちが教えてくれました。満月にしかおこらない現象で、太陽-地球-月が一直線に並んだ時に月が欠けてみえるというものです
があるんだと、うちの農場スタッフたちが教えてくれました。満月にしかおこらない現象で、太陽-地球-月が一直線に並んだ時に月が欠けてみえるというものです
古代マヤ暦とかにもやたら詳しいこのスタッフ。最初はなんだこのマニアックな人たちは!?と思っていましたが最近ではその影響か、少し興味がわいてきました(^^;)
太陽や月のパワーというのは計り知れないものがあるだろうし、農業とも密接に絡んでいます。
太陽光を受けて植物の中で養分が作られて成長していく、とそう単純ではないでしょうが、ともすればそんなことは忘れてしまいがちな最近の大規模農業化シフト。
安心で健康なものづくりという原点に立ち返って畑を増やしていきたいものです
皆既月食は10日の21:45頃スタート、ピークは23:30頃だそうです。
2011年12月07日
イチョウ並木
ついに日本の商業用原発は動いているものが1桁「9」に。
実に83%が停止した状態です。
このままいけば来年春には全原発停止も・・・
わーい!脱原発だー!(*^^*)
と喜んでいる場合ではありません。それに代わる自然エネルギーについて知識を深めたいですね~
九州も節電要請がきましたね。本当に原発は必要だったのか、この目で確かめましょう。

12月に入ってもまだ本格的な寒さとまではいきませんね。
田んぼで玉ねぎの苗を植えていたらカエルがまだいました。
普通ならもう冬眠に入るとこでしょうが、カエルの感覚もずれているかもしれませんね
上の写真は湧水町の農場近くのイチョウ並木です。
きれいですよね~
でもこれ去年の11月22日の写真です。
今年は1~2週間遅れで見ごろを迎えました。
イチョウといえば高校の頃陸上部の練習場にあって、ぎんなんをたくさん落としていました。その近くを走る時はくさくて臭くて息をとめて走っていたことを思い出します
指宿フルマラソンまであと1ヶ月・・・あの頃の筋肉はもはやありませんが、若けぇもんの中で連覇を目指してがんばりたいと思います
2011年12月04日
2011年12月03日
企業秘密のほら穴
これまでうちの生産者で白菜といえば、杉村さんが年末にやっと出てくるぐらいでしたが、今年はすこし早いスタートで霧島市の久木田さんです。
この前久木田さんの畑に行ってきましたが、やはり標高が高いだけあってぐっと気温が低く寒かったです。だから白菜がほかの人より少し早く採れるのかもしれません
久木田さんといえばさつま芋ですが、芋を保存しておく貯蔵庫を見せてもらいました。奥行きが20メートルぐらいでしょうか。土の中に広々とした横穴を掘り、まわりをコンクリートで固めて温度を安定させていました。
気温14℃、湿度80%が最適なさつま芋の保管環境だそうですよ。
約40種類のさつま芋が色とりどりの箱に詰められていました

(株)久木田農園の1年分の収入を稼ぎ出す企業秘密のほらあなに食の家族のカメラが初潜入
隠し撮りの写真を一部だけ公開しましょう。
思いっきり本人の目の前で写していますが・・・








 夏野菜がまだがんばっていましたが、いよいよ終了です
夏野菜がまだがんばっていましたが、いよいよ終了です