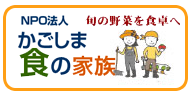2014年02月22日
春草が元気
12~1月という、露地では種まきが難しい時期は過ぎました。
そこで葉野菜などを蒔き始めていますが、これから蒔いても約2ヶ月かかりますね。
4月の中旬ぐらいに新やさいがとれるとなると、そこまでは冬野菜をひっぱらなくてはなりませんが、とてももたないでしょう。

そこで活躍するのは人参、じゃが芋、大根などの根菜類、ねぎ類、さらに去年は3月に入れば前園さんの葉玉ねぎも収穫が始まっています【写真は去年の前園さんの畑】
いつもそんなこんなで何とかなってます。
このぐらいから気温が上がってくると春草ががぜん勢いをつけて野菜におそいかかってくるので、ほったらかしていると足をすくわれますよ。
ホトケノザっていうピンクのかわいい花がありますが、ほうれん草畑で主以上に存在感を増していて今にも食われそうです。
以前はこんなこともありました。
冬のあいだ人参の畑に農業用の不織布をかけて保温をしていたところ、春になっていざ収穫!と白い布をはいでみるとほとんどのニンジンが雑草に負けて姿を消していました。
見えていれば対策がとれるんでしょうが、布をかけていて中が見えなかったんですね。
布がもこもこと持ちあがってきていたので、人参が大きくなっていると思い込んでいたら、なんと雑草が巨大化していたという思い違いでした。
雑草とはつかず離れず、いい関係を保ちたいものです。
2014年02月19日
杉村農園
里芋、九条ネギ、小松菜は出水市の杉村さんが作っています。
今シーズンの里芋は特に不作で掘るのに時間がかかっているようです。
里芋がいる時は1週間前に教えてくれ、と言われてるんですがそれもそのはず・・・

20キロ入るコンテナかごをいっぱいにするのに栄治さんと息子のみちおさん二人で掘り続けて2時間かかるんだそうです。それを4箱収穫!
豊作だったらそれもすぐ掘れてしまうんでしょうが、不作だと芋も小さいし数も少ないしではかどらないです。

掘ったときは親芋に小芋がたくさんくっついてる状態ですから、小芋をばらす(外す)作業をします。親芋は今年の春に植える種芋として温かい場所に大切に保存しておきます
ばらした小芋には根っこがたくさんついてるのでそれも外して、今度はへばりついた粘土質の赤土を落として、やっときれいになった芋から形がわるいものや虫食いのB品などを選別
そこからの袋詰めですから、ここまでの時間はご想像にお任せします。

赤土は雨が降るとすぐにべっとりなって、それが乾くとガチンと固まるので機械類は動かしにくいらしいです。
だから自然と手作業が多くなっているという杉村農園。

晴耕雨読、のんびり、体格のいい栄治さんに対してやせ型で愛犬のタロウのように畑を駆け回り、仕事は段取り命のみちおさんは対照的な性格
そこに叔父の福蔵さん(右)が加わった3人で、今年も美味しい野菜を作ります。【上下2枚は日本ガス情報誌「ひだまり」より】

2014年02月12日
料理長、ニヤリ
今年も紅菜苔ブームですね~
この中国野菜は見た目が紫色で一見するとなんじゃこら!なんですが、さっとゆでて和え物にしても、強火でジャッと炒めると絶妙な食感です。【写真の紫色が紅菜苔(こうさいたい)】

天文館の老舗さつま料理の熊襲亭さんが気に入ってくださってたくさん使っていますよ。
ちょっとこわもての料理長が「こうさいたいはないか、こうさいたいをもってきてくれ」とうわ言のように言います。
この料理長、ギャグのセンスが良すぎて私もとっさには反応できないんですが、そんな時ニヤリとします。まだまだだな、的な感じで。

こうさいたい・・・森のかぞくではごま油と醤油にニンニクを効かせて料理長の弟が出しています。
ここの料理長は「うまい!」とほめるとニヤリ顔をします。

紅菜苔は和洋中いろいろ合いそうですね。
こういう珍しい野菜はだいたい大隅半島は錦江町の真戸原さんです。
小松菜やほうれん草などメジャーな葉野菜はみんながつくるので時期が重なってしまいます。
それで真戸原さんには数年前から独自路線でお願いしていて、コーサイタイ、ター菜、菜花、アスパラ菜、サラダほうれん草、からし菜、ルッコラ、レッドマスタード・・・めずらし美味しい野菜を作ってもらっています【写真右が真戸原えつこさん、左は園山(筆者)】

さてこの夏も面白い野菜をたくさん作ってもらいましょうか~ よろしくお願いします!
2014年02月08日
リベンジ!
今週は全国的にぐっと気温が下がったようで、水曜日は大根占の真戸原さんのところでマイナス3℃、温暖な指宿市でも1℃でした。
今日は関東で大雪になっているそうですね。
横浜で20センチの積雪だと会員さんからのおたよりがありました。
いぶすきには前園さん一家が住んでいますが、農業を始めたばかりの二代目・壮さんも寒さにびっくりした様子でした。
気温のあがりさがりで体調管理もむずかしいですね~
食の家族の生産者は県内各地にちらばっていますが、もっとも暖かい畑は前園さんの畑です。
指宿は霜が降りにくいので露地野菜もほかではできないような作り方ができます。
こっちの寒いところでは11月~1月いっぱいぐらいは種まきができませんが、前園さんの畑では冬でも可能です
そういう好条件の場所なので、旬野菜の早出しがみんなから期待されています。
去年も他の産地に先がけたオクラの早出しが“公約”となっていましたが、ほかの仕事が押し寄せてきて早めに種を蒔けずじまい・・・
今年の農家会議ではリベンジを誓いました。
こんどはしっかりものの壮さんがいるから大丈夫でしょう!

といってもお父さんがしっかりしていないわけではないのでフォローしておきますよ(^^;)
ただ、「この種を蒔こう!」と思って種を買ってきただけで満足してしまうタイプがいるんですよね。
私もこの中に分類されるでしょうが、色々選んで買ってきたわりに種を蒔くのを忘れているタイプです。
特にたねの交換会などで〝タダ"で手に入れた種はよく忘れますね。


忘れたとしても低温・乾燥・密閉して保管すれば何年かもつ種もありますが、それでは余計に緊張感ないかもしれませんね~
今年は種を蒔いたかの確認をしっかりやっていきたいと思います。
2014年02月02日
種をまもろう

先週の農家ミーティングで面白い提案がありました。
野菜の固定種セットをやりませんか?というものです。
一般に流通している野菜、食の家族のものも含めてほぼ固定種ではない、かけ合わせられてできた品種です。

もともとその土地にあった祖先のような種が固定種といわれて、これはずっと種を採り続けていくことができます

湧水町の内海農園では横川大根と国分大根という、どちらも鹿児島の地名がついた大根を栽培していました。

荒れ地だったところを畑にして1年目で、肥料も入れずにでかでかと育ったこのダイコンたちを見ていると、これは固定種の強さというか、かけ合わされたサラブレッドたちがこの環境で育つのは無理かもな、と思いました。

農場主いわく「種は採るから種代はいらない、肥料代もいらない、だから普通のダイコンと同じ値段で大丈夫ですよ」

でも果たしてそうだろうか?
普通の青首大根に比べてこのでかでかのダイコンたちは大根同士の幅が広い!
みんなが社長みたいに広々と陣取っているわけです

葉っぱが大きく広がるし、栄養を土の中でひろく取らないといけないので結果として同じ面積でも3分の1ぐらいしか本数がとれていないはずです

理想としては種代も肥料代もかからないほうがそれはいいんですが、問題は農業経営としてやっていけるか、です
その解決策として固定種セットを食の家族でやってみたいそうです。
野菜セットで安定的に出荷ができていけば、生活が安定してこういう種採り軍団も増えていくんじゃないかと思います。