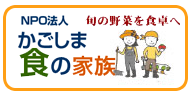2012年10月29日
稲刈りダイジェスト






鎌を使って手刈りしたあと竹で作った馬にかけて天日乾燥
今回のテーマはこのあとの作業、脱穀から精米までをやってしまおうというもの。
掛け干しといえば2週間ぐらいするところを、今回は体験ということで足踏み脱穀機
が登場。


ペダルをリズミカルに踏みながら回転式ドラムをまわし、その周りについている突起によって
稲わらからもみだけがはじき飛ばされていきます。
これだけではまだ精米はむずかしい・・・ゴミがたくさん混じっています。

そこで今後は唐箕(とうみ)が登場。上の入り口からもみを入れ、ぐるぐるとハンドルを
まわすとわらくずなどの軽いゴミが飛ばされていきます。

そこをのぞいてたらゴミがとんでくるぞぉ~
ほーら!

昔の道具はよくできてますね~

もみをきれいにするところまでが完了。待ちに待った澤田さん特製のお昼御飯。
新米おにぎりにお煮しめ、トイモガラのなますなど、「美味しい~」と評判でした。


最後は澤田さんの倉庫にいって新米を精米・・・


こどもたち、精米されて出てくるお米に興味津々です。
精米したてのお米を少しずつ持ち帰りました。
みんなとても良い経験でしたね。
澤田さん、ありがとうございました~

2012年10月24日
アナグマとイノシシ
園山農園からほうれん草にダイコンと一気に冬野菜が採れ始めました。
霧島市の久木田農園からはフライング気味の春菊の登場。
まだ鍋には少々早いか、ネギや白菜がまだ揃いませんね~
と、早くも冬野菜が収穫を迎える農場もあれば、まだ夏の続きを楽しんでいる農場もあります。

日曜日に見学に行った出水市のすぎむら農園では、オクラやピーマンなどの夏野菜がまだ踏ん張っていました。
いや~ それにしても運転手ががんばってくれました。

細い細い山道を小型のバスがのぼること20分。はるか下に東シナ海を見下ろす高台の段々畑が杉村えいじさんが開拓した自慢の畑です。

赤土の粘土層のため種まき機も動かせず、種は手で蒔きます。
芽がでるまでものんびりなら、芽が出てからの生育もスローペース。
山の生活と野菜の生育がぴたりと合ったような農園です。
ただしその優雅な生活を脅かす存在が!

「あなぐま」です。
なんと一晩で秋じゃが畑を食い荒らしてしまいました。
たぬきに似た動物で、しばしば出没するらしいです。


そんなアナグマも箱型の罠によってあえなく御用。
また平和な生活が戻ってくると思いきや、イノシシ害も大変らしいです。
すぎむら農園から山道を下る途中、一頭の大イノシシが猟師の軽トラに捕獲されていました。
農家と動物との共存は山暮らしでは大きなテーマです。

午前中の澤田農園での稲刈りはボリュームが大きすぎるのでブログでそのうち紹介します。
とりあえずはお米作り体験終了!お疲れ様でした。

2012年10月17日
久しぶりの雨
ここ数週間は乾燥が続いていたため、雨が降ってほしい反面、稲刈り真っ盛りの米農家はちょっと休憩になったことでしょう。
生育中の玉ねぎの苗やキャベツ、白菜などが一気に勢いづいてくるはずです。


これは玉ねぎの苗。水をしっかりかけています。
にんじん、ダイコンなども日に日に大きくなっていて、味見をした感じでは美味しいです。
野菜は収穫時期が重なってしまうと収穫が追いつかないということがあるので、少しずつ種まき時期をずらして蒔いています。
にんじんひとつとっても一番早いもので8月上旬に種をまいていて、それが10月中に収穫になる最速のタイプです。
今蒔いたものは冬に入るので時間がかかり収穫は春になります。
人参はタイムリーに収穫しなくても、ある程度は土の中においたままにできるからいいです。
難しいのは葉野菜!

季節がいいときは30日を切るぐらいで収穫になり、収穫適期は2~3日間ぐらいでそれを過ぎると大きくなりすぎます
先週木曜日に収穫した小松菜がベストタイミングでした。袋にしっかり収まるぐらいの大きさで、あれぐらいでいつも収穫するのが理想的♪
今週月曜日に収穫したのはもう袋から出ていて、スーパーには売っていないサイズ。
そして明日収穫するするのは・・・1週間前の小松菜と同じ日に種まきした小松菜ですが、その大きさははるかに違うでしょう。
しかも雨が降りましたからね、どんなサイズになっているのか怖いです
このように「いつごろ」「どれぐらいの量を」収穫するのかをあらかじめ決めておいて、そこから「今の時期なら収穫まで何日ぐらいかかるか」を逆算して種を蒔かないといけないんですね。
農業は実は頭使うんですよ~
2012年10月14日
機嫌を損ねる
ところがコンバインがトラブル

半日で済むはずの機械型稲刈りはまさかの日没コールドに終わり、仕切りなおしとなりました

機械はこれだから困るんですよね~

いまどきの稲刈りといえば昔のように家族や親戚中で集合して、みんなで鎌で手刈りするなんてことはそうそうしません。
コンバインという大きな収穫機があって、田んぼを走りながら刈り取って、脱穀(
 もみの状態にすること)してくれます。もみの状態で持ち帰って乾燥機に一晩かけてしまえば翌日には新米が食べられるというわけです。
もみの状態にすること)してくれます。もみの状態で持ち帰って乾燥機に一晩かけてしまえば翌日には新米が食べられるというわけです。そうでなければバインダーという結束機でわらを束にして、竹にかけて干しておくというパターンもありますよね。これはまだよく見る光景(*^^*)
天日乾燥は2週間ぐらいかかります

大型機械で刈る場合は人手は要りません。
田んぼの中にいるのはコンバインの運転手ひとり。なんか寂しいですね

この機械が登場するのは年に1度だけですから、動かしていないとトラブルも多いのです
 昨日は終始ご機嫌がわるく、最後まで本調子とはいきませんでした。
昨日は終始ご機嫌がわるく、最後まで本調子とはいきませんでした。家族総出で手刈りしていれば十分終わったであろう広さですが、機械の機嫌を損ねたがために持ち越しとは・・・便利さを追求したあまりなんという失態だろう

次のの日曜日は出水で澤田ファミリーと一緒に鎌でお米を収穫して、今じゃ珍しい脱穀機も体験します

澤田さんも大型農家。ふだんはこんなものは使わないのでデモンストレーションではありますが、昔ながらのお米の収穫を体験してこどもたちに実感してもらうことは大切だと思います。
2012年10月11日
野菜をかたづける
9月中旬に種をまいた玉ねぎの芽が生え揃ったというところですが、乾燥させてはまずいです。
毎日でも水をやって苗をしっかり作らなければなりません。
時間とか労働力を考えれば、1回の雨がもたらす経済効果は大きいです。
乾燥する前に収穫を迎えた野菜もあります。


小松菜は種まきのタイミングがよかったのか虫食いも少なくてきれいです。
だいこんもぐんぐん大きくなっています。
少しずつ秋の野菜に入れ替わりつつあります。
季節がかわる、野菜がかわる、畑の様子がかわる
と、こういう時期は秋の野菜を収穫するかたわら夏野菜を片付けていきます。
収穫が終わった野菜を片付けるというのはけっこう面倒な仕事です。

たとえばこのツルムラサキの畑。
これを片付ける場合に、まずビニールマルチをはがさなくてはいけませんが、このままでは雑草の根がすごいのではがせません。

そこでこんな機械を使います。

耕うん機を使って雑草をねこそぎ取り除いてしまいます

これならマルチを回収できますね。
こういう石油製品は使わないに越したことはないんですが、雑草取りの手間を考えたときにどうしても省力化で必要になってきます。
農薬にしても化学肥料にしても現代農業は石油に頼っている部分は否めません。
土に還らないこういうものは極力使わずに、環境への負荷を考えたいところです。


年に2回、この廃マルチを回収する日があります。
この山を見たら、これは一体どこへ行くのだろうと考えますね。
食の家族の生産者は農薬や化学肥料を使わないことはもちろんですが、これまで極力こうしたマルチなども使わないような工夫はしてきたし、今でもほとんど使わない生産者もいます。
それがすぎむら農園です。
種まきは手でぱらぱらと、草取りは手で取ったり草かきで削ったり、畑はクワで耕し・・・とさすがにそこまではないですが、あの畑の広さでそこまで手作業ですか!?という今じゃ珍しい農園を21日に見学しにいきます。
一緒に江戸時代にタイムスリップしましょう 笑
笑
2012年10月08日
若けぇもんの会とは?


農業共済新聞より若けぇもんに原稿依頼がありました。
で、紙面をどんな感じで作ろうか、そういう話でした。
右手前が東京からお越しの農業共済新聞の安田さん。
左手前は園山、安田さんのうしろが若けぇもん会長のすぎむらさん
ほかに若けぇメンバーが集まって熱いぎろんを交わしました。
若けぇもんの会とは有機農業に関わりのあるメンバーが中心となっていて、
食と農に関心があればだれでも入れる会(年齢もいちおう不問)
部会制になっていて、それぞれ担当の宴会部長、マラソン部長、登山部長、新エネルギー部長などがいます。
もちろん遊んだり飲んでばかりではなく、ちゃんと勉強会やほ場見学もしています。
会長、副会長、事務局、会計、最高顧問などがいますが、基本的に一番偉いのは宴会部長のしばちゃんです。
事務局をかごしま食の家族で園山が担当しています。興味がある方はHPからメールでご一報くださ~い。


この日はメンバーが育てたオクラやピーマン、三尺ささげなどの有機野菜を使った料理を用意していただきました。
有機野菜のバーニャカウダは美味しかったです。下は久木田農園の有機むらさき芋とにんじん芋を使ったアイス。これも
 でした。
でした。

2012年10月06日
虫取りの秋


今湧水町の畑で問題になっているのが
『ダイコンサルハムシ』
その名の通りダイコンなどのアブラナ科の葉についてぼろぼろに食い尽くしてしまいます
すでにキャベツやブロッコリーの苗が食べられ始めています。



ひとたび出始めると繁殖力がすごくて、白菜はもうそこでは作れなくなりました。だから白菜担当は杉村さんや久木田さんに任せています。
園山農園はキャベツやブロッコリーを死守します
ただ一点サルハムシに弱点があるとすれば“飛べない”ことですかね
地上戦なら人間に勝機もあります。
収穫まであと1ヶ月。地を這って退治します。

2012年10月03日
手作り醤油
今日はよりによっての快晴で、醤油作りをはじめた「いつ子さん」が暑い中でまずは麦を炒るところから始めました。見学者が二人。
手作り醤油は根気がいる作業です。

醤油作りはもともと「はるえおばあちゃん」がしていたものを、いつ子さんが引き継いでやってきましたが、やはりおばあちゃんの技を覚えるのには苦労したようです。
小さい頃から我が家の食卓に上るのはいつも決まってこの琥珀色の醤油でした。


世の中の醤油がこんなに黒いものだとは、およそいい年になってから知りましたね(笑)
去年ぐらいから原料になる有機小麦や大豆を湧水町の農園で自家栽培に取り組んでいます。
小麦も大豆にしても作ってただ販売するにはあまりにもお金になりません。だから休耕田で作ったり、生産者に補助金を出して作ってもらっているのがこのニッポンです。

自給率は小麦が14%、大豆は6%というから、いかに外国からの輸入に頼っているか分かりますね。外国は日本の数百倍とか、それ以上の規模で作っていますから値段がとても安いんでしょう。
でも昔から農家がやっていたように野菜やお米の裏作で麦や大豆を作って、それをしっかり加工して国内に販売すればまだ自給率を上げられるとも思います。
ところでこの度、私の娘が誕生しまして、いつ子さんに二人目の孫ができました
ひとつの時代の流れを感じます。
受け継がれてきたものが、また今度は誰かの手によって引き継がれていくのでしょうか。
醤油つくりはまた10日後に第2ラウンドです