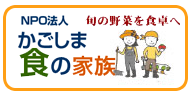2013年01月22日
規格外野菜とは
去年の9月ごろから、「農商工連携人材育成塾」というなにやら難しい塾に通っているんだが、そこではいろんなことを教えてくれる。
たとえば農家が生産、食品加工、販売流通までを手がける6次産業化の推進。
生産は1次産業、加工が2次、販売は3次であって、それを足したりかけたりすると「6次」となるという意味だ。
農業をしながら誰もが悩まされるのは、一般に出荷ができない「規格外品」の扱いだ。

そこでこれをなんとか活用できないか。そんなことをテーマにして人材育成塾では取り組んでいるところだ。
農家のお母さんたちが漬物にしたりとか干し大根、ジャムやマーマレードなどいろんな加工品を作っているが、言ってみればそのような形でどんどん商品化して売っていく。
畑に捨てているものを有効に利用して所得向上につなげられたらよいと思う。

であるならば間に入る流通ががんばってその妥協点をさぐらないといけないと思う。いろんなアイデアを流通が考えることも大切なことではないか。
たとえば農家が生産、食品加工、販売流通までを手がける6次産業化の推進。
生産は1次産業、加工が2次、販売は3次であって、それを足したりかけたりすると「6次」となるという意味だ。
農業をしながら誰もが悩まされるのは、一般に出荷ができない「規格外品」の扱いだ。

そこでこれをなんとか活用できないか。そんなことをテーマにして人材育成塾では取り組んでいるところだ。
農家のお母さんたちが漬物にしたりとか干し大根、ジャムやマーマレードなどいろんな加工品を作っているが、言ってみればそのような形でどんどん商品化して売っていく。
畑に捨てているものを有効に利用して所得向上につなげられたらよいと思う。

であるならば間に入る流通ががんばってその妥協点をさぐらないといけないと思う。いろんなアイデアを流通が考えることも大切なことではないか。